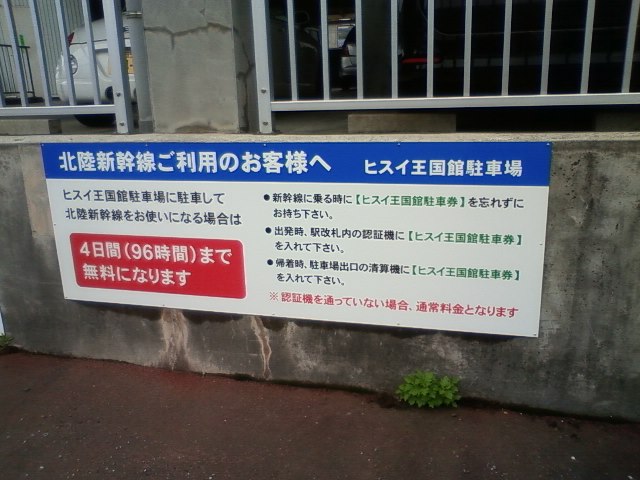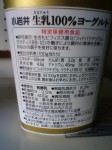blog
車検時にショッカーブソーバーのオイル漏れを指摘され自分で交換を決意。
純正品1本と、今回採用したProcomp ES9000 4本がほぼ同じ金額。
フロアージャッキで馬を掛け後輪を2本外す。
後輪は17mmのメガネレンチにパイプを継ぎ足してパワーアップして外しました。
ただ左側はレンチを入れるスペースが少なくやっと外しました。出来ればメガネレンチを
少し薄く削った特殊工具を作っておいた方が作業がスムースでしょう。
固定部の上部スリーブが少し長いのでグラインダーで削りました。
交換時はデフにフロアジャッキを当てておきながら作業しました。
今回長さ調整できるヒモを使いました。リュックなどにつけて、調整した長さで
固定できるヒモで、緩めるときはワンタッチでできるやつ。
これでショックを縮めて固定し、取り付け位置まで持っていったらひもを緩めて
定位置に設置しました。
前輪は下のブッシュに挿入するスリーブを後輪同様グラインダーで削ります。
それとブッシュ自体も幅が長いのでカッターでカットしました。
前輪ショックの取り外しは、馬に掛けた後下側のボルトのナットを外し、上側のナットを外してから
ショックの上側固定部の隙間に木切れを挟んでショックが縮まないようにしました。
ロアアームにジャッキを当ててアップ、その状態でショックにヒモを装着してジャッキを下げます。ショックは縮んだままなので上部の穴からショックのねじ部が抜けてきます。一回でねじ穴の下までショックのトップが抜けないかったので2回繰り返して上部の隙間を
作りました。
左側は簡単に外れたのですが、右側が厄介でしたが後で左右の取り外したショックを比較したら
長さが全く違っていました。左はすっかりへたっていた感じです。
取り付けはまたあのヒモでショックを縮めて下のボルトを取りつけて上の穴位置にセットします。
前輪の上ボルトはブッシュを挟むと最初のねじ山が掛かりずらい感じでした。すこしブッシュを
押し込んだ感じでねじ込みます。締め付けは走行状態で締めることのようなのでロアアームに
ジャッキを掛けて馬が少し浮くくらいにして上側ボルトを締めこみました。共回りしないように
頭をモンキースパナで押さえて14mmのメガネレンチで締めました。モンキーはうっかりナメテ
しまわないように注意します。
変な体勢での作業が続くので翌日は体が痛くて参りました。
交換後の感触はちょっとふわっとした感じでしょうか。乗り心地は良くなっています。
かと言ってコーナーが不安定と言うことはないでした。思ったより純正が固いショックだった感じではあります。
足回りの作業は危険な事も多いので十分注意して行いましょう。
先シーズンの冬、家のメインストーブがやけにうるさくなってきました。
今年もそろそろシーズンを迎えるので、思い切って分解清掃、場合によっては修理を
試みました。ストーブメーカーでは推奨していない(禁止している?)事かもしれないと
思うので参考にして作業したりしないでください。
完全にモーターの回転に付随して騒音を発しているので、そのあたりを
分解してみました。
うちのはFFのストーブなので壁から外すのに手間がかかります。しかし最初に設置したのも
自分なので、どうなっているかはわかっているのでここは簡単です。
あけてみると結局、回転しているのは送風のブロアモーターしかないんですね。
モーター単体にするのにファンの部分がなかなか外れません。さびなどで焼きついています。
ファンは軸にイモネジが付いていてそれも外します。
モーターの軸だけにしてベアリングを持って回転させると
片側のベアリングに滑らかさがまったくありません。回転が持続しないのです。
ベアリングもまた外します。これを取り換えればよいはず。
ベアリング・・・626ZZ に交換
外径 19mm
内径6mm
幅 6mm
元のベアリングはZZではなくゴムシールドでした。なので高温でボコボコになっていました。
もう片側も同じベアリングですが問題なさそうなので継続使用します。
・・・・ベアリングの外側にホール素子用のエンコーダー磁石が装着されていますので
それを外さないとこちら側のベアリングは外せないから無理しませんでした。・・・・
ベアリングもなかなか外れなかったけれど、根気強く軸を磨いたりして外しました。
外してみるとそれほどきつく圧入されいるものでもなさそうです。取り付け時は
スムースに取り付けられました。
ストーブをすべて組み立てて、電源ON。
素晴らしく静かな動作です。
買った時はこんなに静かだったんですね。
以前ヨーグルトでクリームチーズを作ったのを思い出して、こんどはチーズケーキを作ってみました。
ヨーグルトをキッチンペーパーにあけて、冷蔵庫に3日くらい放置。
かなりの水分がなくなり、クリームチーズぽくなりました。
今回は炊飯器でご飯を炊くのと同じに、チーズケーキを焼いてみました。
・クリームチーズ(ヨーグルトだけど)
・生クリーム 180g
・砂糖 100g
・薄力粉 大さじ2
・レモン汁 大さじ2
これを炊飯器にクッキングペーパーを敷いて投入。
3回ぐらい炊飯OKを繰り返しました。
おかまを炊飯器からはずして自然冷却。
ひっくり返して取り出します。
ちょっと柔らかめだけど、レモンが効いて思っていたよりおいしくできました。
microSDカードのアクセスができるボードを試作しました。
すでに製品化したEthernet system board に積み重ねられる様に
コネクタが配置されています。
現在、ファイルアクセスはできます。周辺のインターフェースを整備して
コマンドを組み込んで、外部命令からmicroSDカードにアクセスできるように
考えています。
また、ここで使っているPIC24FJ64GA004というCPUは、RTCC(リアルタイムクロック)を
搭載しているので、時間の管理もできます。
・・・ファイルシステムを操作する時にはファイルのタイムスタンプが必要になるので
RTCCは当然と言えば当然かもしれませんが・・・
これで、LANとメモリーカードの制御が可能になりました。
先日、入浴中に突然給湯器の表示が「632」となってエラーしてしまいました。
どうも追い焚きが出来なくなった様で、エラー内容は「循環ポンプエラー」となっていました。
今年で14年使用してきましたが、不具合は初めてです。
ともかく給湯器を見てみました。
とりあえずこのモーターに電圧が出ているか確かめました。
スイッチを入れても何の音も変化もありません。装置が全く動作していない感じです。
端子電圧もまったくありません。
内部のごみの具合も確認するためと思い、ポンプをはずしてみました。
それと単体動作するのか?
カバーを外して分解してみます。
カバーは水の通り道になっています。中にはステンレスの遮蔽板とゴムパッキンがサンドされて
いました。このゴムパッキンがなんだかボロボロになっているように見えます。
しかしよく見ると水垢のような堆積した細かいゴミのようで、ゴム自体は
ちぎれいてる所は少しだけでした。
水の中でゴムパッキンについたゴミをきれいに指で落として、もどします。
この状態でポンプ単体でAC100Vを印加。回転するかチェック。
きれいにしたゴムパッキンと洗い落した堆積ゴミ。
ゴムパッキンの内部の開口部分が劣化してちぎれ気味になっています。
ここまでの結果では、このポンプが動作しないとは思えない。添付してたあった分解説明図と
動作フローをじっくり見てみると、ポンプが動作する前に、水流センサーがOFFであることを
確認している。このセンサーが非常に怪しい。
このセンサーがありました。
奥なので循環ポンプは外しておいて正解。
ちょっと手が入りづらいですが、流水センサーを外せます。
センサーを外して中を拝見。
 おっ。さっき循環ポンプの中にあったゴムパッキンに付着していた
おっ。さっき循環ポンプの中にあったゴムパッキンに付着していた
ゴミではないか!しかもデカイ。
ごみを取り除いてセンサーの動きを確認。
これが外側のリードスイッチ(磁力で接点がONになる)をON/OFFして水の流れの有る無しを
検出しているようです。
すべて元に納めて風呂の追いだきチェック。
正常に動作しました。
今日は安心してお風呂に入れそうです。
機械に添付してあった分解整備図面がとても役に立ちました。
エラー表示のシーケンスまで記載されていたので非常に良かった。
しかし、もうそろそろ買い替えの時期かもしれないけど、うちは二人しかいないので
年数の割にはかなりきれいな方かもしれません。
循環ポンプのゴミをきれいに取り除けば、結構イケそうな気がします。それに、ポンプのごみは
ポンプの納まり場所からしてその状態で掃除ができそう。風呂釜洗浄剤の前に
ここを掃除しておくのはかなり有効と感じました。
先日、試作していたEternet System基板の製品レベルの物が出来ました。
EEPROMも搭載してWebページが表示できます。現状ではMicrochip Technologyの
サンプルページが表示されます。このWebページからIPアドレス、MACアドレスの
変更が可能です。
実験的にLCDモジュールで起動時のIP表示が出来るようになっていて
IPアドレスはDHCP機能を持っているので、ルーターなどから割り当ててもらえます。
TCP/IP通信で外出先からこの基板にアクセスして、LCDに文字表示できる
アプリも作成可能です。つまりボードのI/Oを遠隔地から制御可能となっています。
現在、仕様をまとめながらファームウェアをアップデートしています。
ネットワークに接続してコントロールできる基本基板ができました。
TCP/IPで接続してI/Oを制御出来ます。
自宅にある機器のスイッチにこの基板をセットしておいて、外出先から
セットした機器のスイッチをON/OFF出来るということです。
この基板は、その機能の中心部分となるコンピュータとネットワークの部分を持っています。
・マイコン ・・・ PIC18F67J60
試作基板製作にはスルーホールをあけるのが大変でした。
分かっていましたが、試作できるかどうかの試験的な試みも加味して挑戦。
スルーホールを0.4mmで開けて、0.32mmのワイヤーで表面と裏面をハンダ付けしています。
面実装部品はすべてリフローしています。
穴あけは大変でしたが試作としては十分な出来になりました。時間はかかりましたけど・・・
この基板はコネクタで別基板を重ねて接続できるようにして、いろいろな機能のシステム基板の
ベースとして使いたいと考えています。